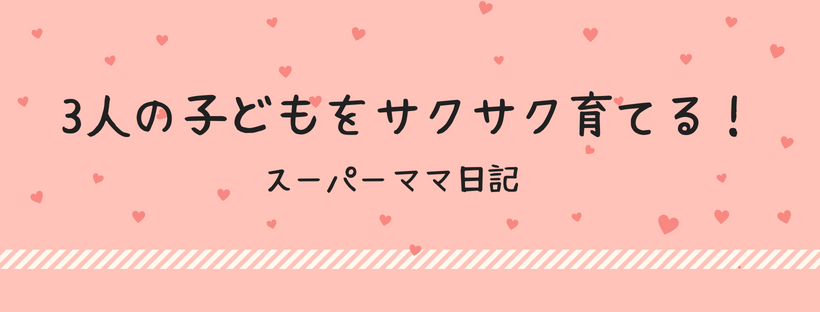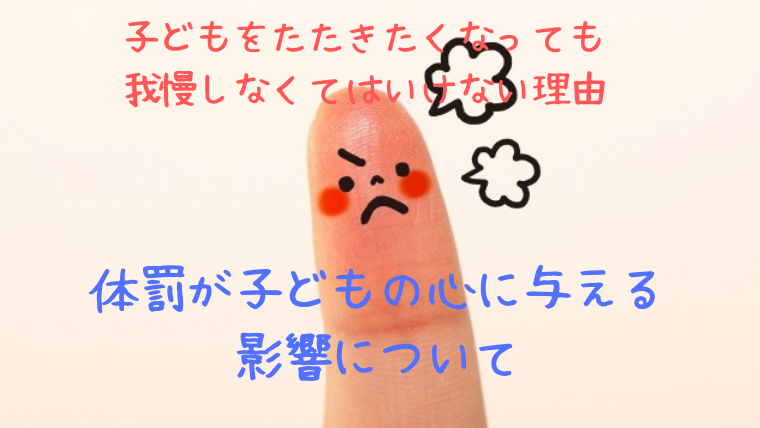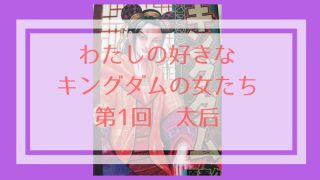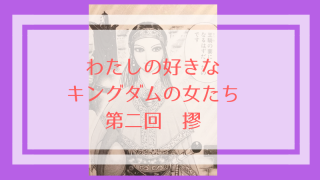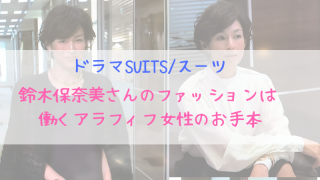子育て中のイライラ。
とくに、まだ言葉での意思疎通が難しい時期は、思い通りにならないことが多くてイライラが募ることもありますね。成長したら成長したで、なかなか言うことを聞かないことに腹を立てることもあるでしょう。
そんなとき、どうにもならなくなってつい子どもに手をあげてしまう親も多いようです。私自身、子どもが小さいときは、そんな気持ちに襲われることもありました。
でも、手をあげたことは一度もありません。というのは、私が、殴られて育ったため、体罰で子どもに言うことを聞かせることの弊害を実感しているからです。
ワンオペといわれるように、たったひとりで子育てしていると、イライラ、キーッとなってしまうのは、仕方ありません。大変さはほんとうに理解しています。叩いたあとは、きっと後悔していると思うのです。辛いですよね。
手を挙げるのはよくないとわかっていても、ついやってしまって後悔して自己嫌悪。それがさらにイライラを生んでしまって、気付くとまた手を挙げてしまう。
感情的にカーッとしてしまうのですよね。きっと機嫌のよいときなら笑ってすませられることもあるのでは?
叩くことが当たり前になってしまう前に、なんとか辞めたいですよね。
親が感情にまかせて子どもに体罰を与えることが習慣になってしまうと、子どもの心にどんな影響があるのか?
私自身が克服するためにとても苦労した(まだ治らない点もあります)心のクセをご紹介したいと思います。
読んでいただけたら、きっと、体罰はもうやめようと思えるはずです。
どんな体罰だったか:私の場合
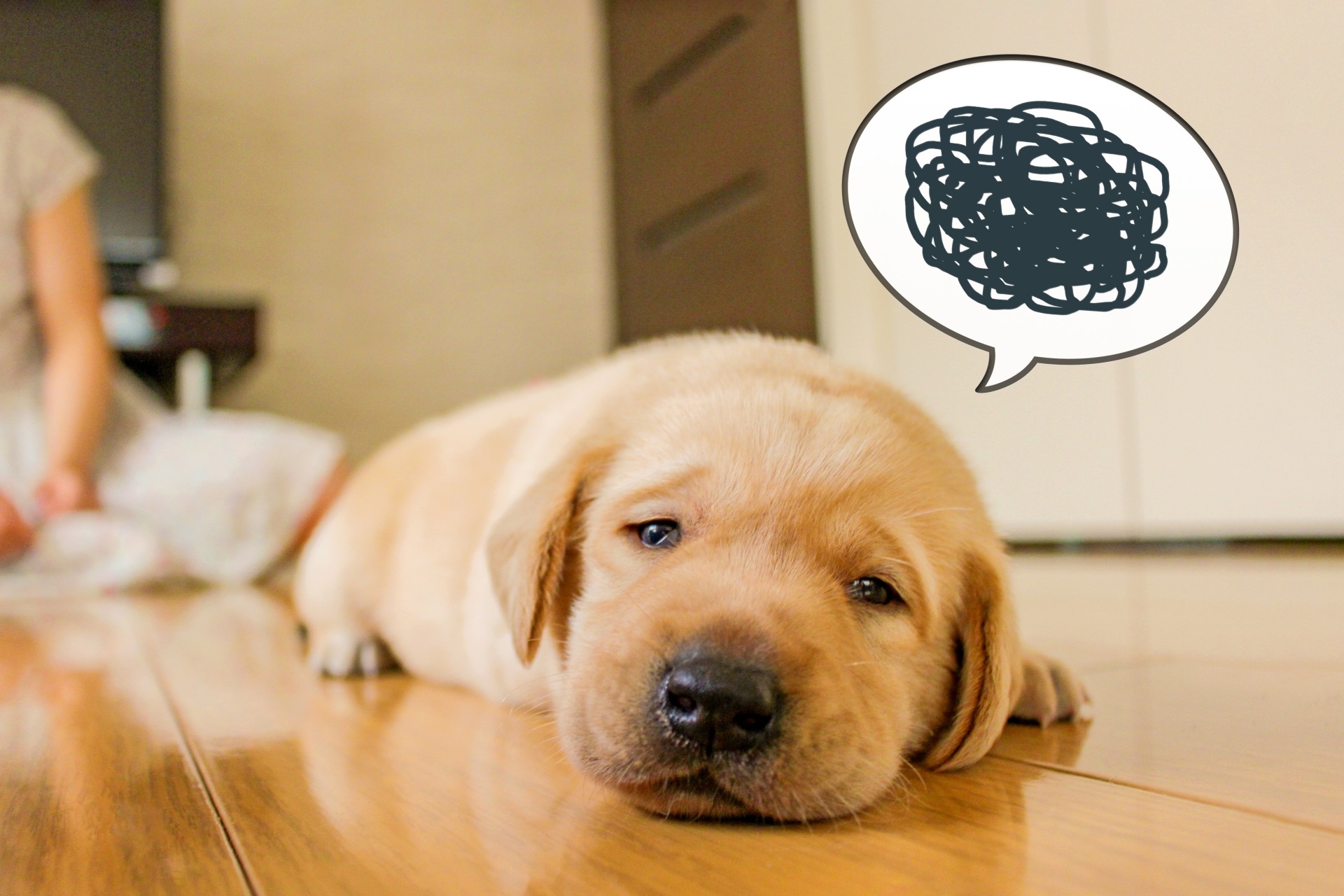
私は、父から殴られて育ちました。記憶が残っているのは小学生くらいからでしょうか。それ以前にもあったのだとは思いますが、記憶がほとんどありません。
父のためにも断っておきますが、基本的には、子煩悩な優しい父です。でも、叱られるときは、必ず殴られました。優しく諭すように言い聞かせるという選択肢は、父の中になかったようです。「子どもなんて犬畜生と一緒で、体で覚えさせなきゃわからないんだ」というのが父の持論でした。
また、父の怒りを引き起こすスイッチがどこにあるのかが、幼い私にはわかりませんでした。というのも、同じことをしても叱られることもあれば、まったくお咎めなしのこともあったからです。そのときの機嫌に左右されるものでした。仕事のストレスなどもあったのでしょう。
小学生から中学生までは、ほんとうによく殴られました。高校生になってからは、さすがに減りましたが、それでも皆無ではなかったと記憶しています。頭を平手打ちにされることが多かったです。時に蹴りが入ることもありました。
父に逆らえない母は、殴られ続ける私を助けてくれたことは一度もありませんでした。じっと我慢して、叱られる時間が過ぎるのを待つのみ。誰にも頼れない、誰も助けてくれない、そんな気持ちでした。
体罰を受けたことで後天的に得た性質
殴られるのはとても怖いです。私自身、殴られて育ったことで影響を受け、後天的に得たと思える心の傾向があります。おおまかに3つ、ご紹介したいと思います。
自分の意見を言えなくなる
冷静に論じることができない場では、反論してもさらに殴られます。火に油を注ぐだけ。言い返したいことがあっても、口にできません。そのような状態が続くと、だんだんと考えることを放棄するようになります。言っても聞いてもらえない、言ったらよけいに怒られる…となると、鈍感になることがいちばん身を護れると子ども心に悟るのでしょう。怒られていないときであっても、自分の言ったひとことが父の逆鱗に触れる可能性もあります。子どもにとって親は絶対的な存在ですから、余計なことは言わないでいることが最良の選択なのです。
そうなると、親がいないところでも、だんだん意見を言うことを避けるようになってきます。意見がない状態がデフォルトといったら伝わるでしょうか。遠慮しているわけでもなく、ほんとうにどちらでもよいのだと思っているのですが、周囲からは何を考えているのかわからないと言われることもあります。
社会に出てからは、学生時代と比べてさらに自分の意見を求められることが多くなります。明確な主張のない自分は、なんて中途半端な人間なのだろうという意識に苛まれていました。だから、爽やかに自己主張できる人に憧れました。
今でも自己主張は苦手で、なかなか克服が難しいです。
無価値感に苛まれる
ほんとうに自分には価値がないと感じるようになります。決してかわいそうだねと慰めてもらいたいわけではありません。心の底から、自分には価値がないと思うのです。
大切なものは、だれもが丁寧に扱うと思います。ブランド品が白い手袋をはめた店員さんに丁寧に扱われるように。
ところが、優しく撫でられるどころか、バチンバチンと思い切り殴られるのです。自分は大切にされていないと無価値感を持ってしまうのも当然ではないでしょうか。無価値感にむしばまれると、自信も持てず、どうせ自分はこの程度…と自分を低く見積もってしまいます。
根拠のない自信のある人は成功すると言われますが、無価値感を持ってる人は全く逆のパターン。根拠のない「絶対成功しない」自信だけはあるのです。
なにかチャレンジしようと思っても、どうせ自分はうまくいかないだろうと感じていたら、成功するわけがありませんよね。
余談ですが、体罰はたぶん暴言とセットになっているはず。この暴言は、子どものセルフイメージに直結するので絶対にやめてほしいです。
機嫌を損ねることが何より怖い
自分のせいで人の機嫌を損ねることがほんとうに怖くなります。機嫌を損ねるくらいなら自分が我慢しようという思考になりがち。気付いたらいつも損な役回りに。
自分を大切にしないと、人からも軽く扱われるとよく目にしますが、ほんとうにそのとおりだと感じています。それでも、頭では理解していても、幼いころからの思考を変えるのはなかなか難しいのです。先にあげた無価値感とも繋がりますが、自分を大切にするというのがどういうことか、正直わからないのです。
親に思うこと

先にあげた3つに悩んでいる人を想像してみたら、なんだかとても暗そうで、幸せとは縁遠い人が浮かんできますね。実際そうなのかもしれません。幸せは、人との対比で相対的に決まるのではなく、それぞれの基準で決めるものだと思うので、私は今、幸せだと思っていますが。
もし、わが子がこんな状態になってしまったら……なんとも切なくないですか?
両親には、もちろん感謝もしていますし、いつまでも元気でいてほしいと思ってます。どんなに殴られても父のことは好きでしたし、恨んだこともありません。当時、両親もまだまだ未熟で、そうするしかなかったのだろうと思いやることもできます。
でも、一方で、心から甘えたことは一度もありません。父の体罰から守ってくれることがなかった母にも、安心して甘えたことがありません。悩み事などを相談したこともありません。どうしても越えられない壁があるんですよね。
ちなみに、親は、私がこのように思っていることをまったく知らないと思います。娘が家に寄り付かない原因が、まさか自分たちの体罰と見て見ぬふりにあるとは夢にも思っていないでしょう。
まとめ
親子の形は様々ですから、体罰をしなかったからといってすべてがうまくいくわけではないでしょう。でも、体罰は、親が思う以上に子どもの心を蝕みます。そして、ひとたびダメージを受けた心は、回復させることが難しいです。
いま、体罰がやめられない方、手をあげたくなったらどうか一呼吸置いて、ぐっとがまんしてみてください。体罰は、たしかに簡単な手段です。でも、長い目でみたときのマイナスがあまりにも多いです。それは、親にとっても子どもにとっても。
多分、手をあげても、子どもは親を見捨てないでしょう。反対に、そんな親がかわいそうだと甘んじて体罰を受け入れるかもしれません。でも、温かな親子の絆は生まれませんし、子どもにとって家は、安心できる居場所にもなりません。
親が育児でイライラを募らせないためのリフレッシュ方法を見つけることも大切ですね。時間的な余裕がない、金銭的な余裕がないなど、リフレッシュすることすら難しいこともあるでしょうが、抜け道もきっとあると思います。私の場合、子どもが寝静まったあとでひとりで食べる深夜のアイスなども、十分ご褒美になりました。
さみしい思いをする子がひとりでも減りますように……そう思ってます。